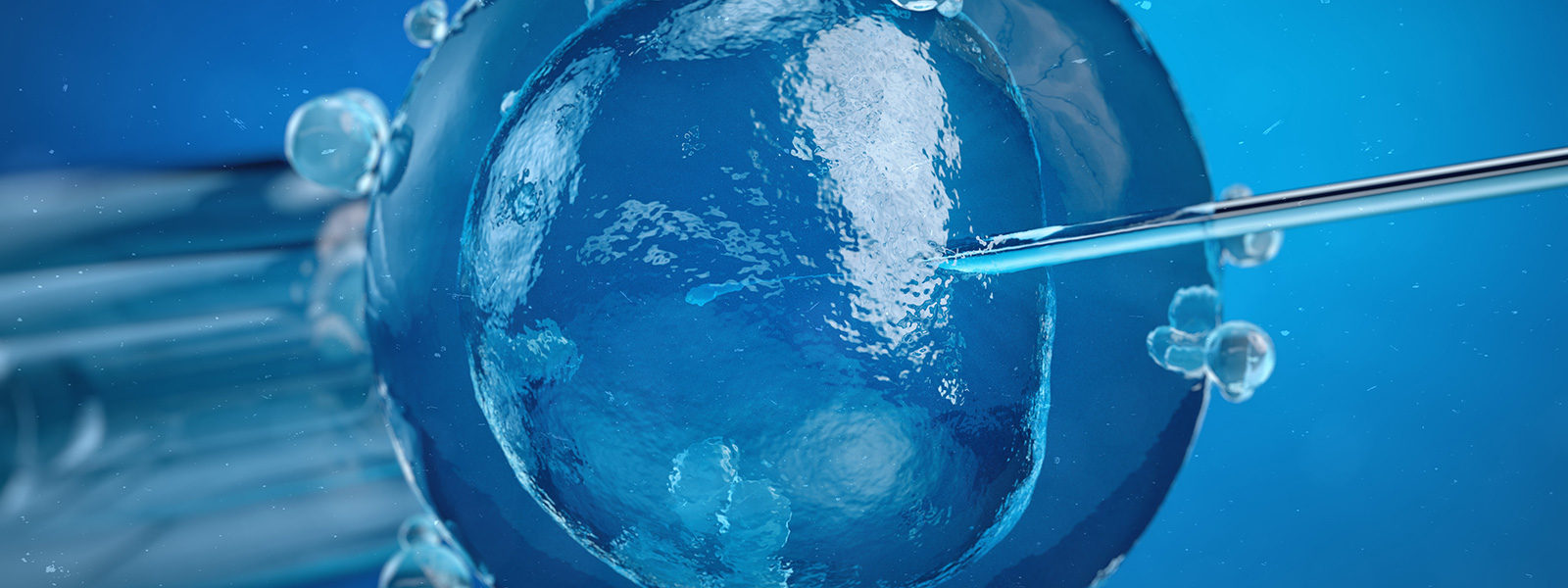不育症
不育症とは
流産は約15%の頻度で生じますが、高年齢や流産回数が多くなるにつれ、その頻度は増加します。2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡) がある場合を不育症と定義します。習慣(反復)流産はほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。不育症はより広い意味で用いられています。
不育症の検査・治療
-
子宮形態検査
超音波検査、子宮卵管造影検査、必要に応じMRI検査などを行います。形態異常がみつかった場合、一部が手術の対象となります。ただ現時点では手術をした方がいいという明確な根拠はありません。
-
内分泌検査
甲状腺ホルモン異常や糖尿病の有無を評価します。異常がみつかった場合は、内科専門医の治療をうけ、十分にコントロールしてから次回妊娠に臨みましょう。 妊娠後も引き続き治療が必要です。
-
抗リン脂質抗体・凝固因子検査
これらがありますと血栓ができやすくなる結果、流産の原因になります。アスピリン、ヘパリン等の抗血栓療法を行います。
-
夫婦染色体検査
夫婦で染色体に構造的な異常がありますと、受精卵の遺伝子に欠損や重複が起こりやすくなるため、流産しやすくなります。染色体異常は生まれつきのものですから治療はできません。しかし、流産を繰り返しながらも、最終的に出産までいける可能性は、染色体正常カップルと比べても決して低くないことがわかってきています。
上記検査の結果、原因がはっきりとした方は治療を行います。原因不明(偶発的な流産をくり返したと思われる方)の方は何も治療をしなくても、次回の妊娠で成功する確率は高いです。